いわゆる負担付贈与の実務論点② 収益物件(貸家建付地)の建物の評価方法は?
問題の所在
以下の事例を検討する:
・夫と妻と娘2名。
・夫と妻が世田谷区内にアパート物件(貸家建付地、土地と建物)を共有で保有していた。
・当初の建設資金は、金融機関から、各々の名義で借り入れている
・妻が逝去し、遺産分割の結果、長女が当該貸家建付地と借入金をセットで相続することになった(★父は自宅を相続)が、そのままだと当該貸家建付地は娘と父と共有になるため、相続後に父の共有持分を長女に無償譲渡(注1)することにした。
・被相続人の準確定申告書によれば、貸家(=建物)は平成13年に取得(建設)し、旧定額法にて、当時の償却率を適用し、継続して償却している。
収益物件であるアパート物件(土地と建物)を残債(借入金)とセットで贈与する場合は、いわゆる「負担付贈与」に該当するが、計算上の留意点として、後述の解説記事などでは3つの論点が挙げられていることが多い:
- 負担付贈与の場合では、取引金額といっているので、土地も同様であり、(路線価ベースで算出した)相続税の確定申告時に算出した相続税評価額そのままでは不適当で、それを1.25倍(又は0.8で割り)、公示価格に引き直して算出する必要がある
- 債務には、住人の敷金、保証金もカウントする
★銀行借入金が無くても、これがあるだけで負担付贈与の通達が発動される蓋然性がある。 - 贈与をした側の者も、債務分は所得税の収入にカウントされる
上だけ見ると、「土地は個別計算があるが、建物にはコメントがない。。。ので、建物は、通常通り、相続税評価額ベースでいい」、と思ってしまうが、それは間違い。
すなわち、収益物件の負担付贈与では、鉄板である以下の通達の中で、しれっと明記(!)されている。
負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等及び家屋等に係る評価並びに相続税法第7条及び第9条の規定の適用について
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/890329/01.htm
(以下、一部抜粋。太字は筆者加筆)
1 土地及び土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)並びに家屋及びその附属設備又は構築物(以下「家屋等」という。)のうち、負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得したものの価額は、当該取得時における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
ただし、贈与者又は譲渡者が取得又は新築した当該土地等又は当該家屋等に係る取得価額が当該課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、当該取得価額に相当する金額によって評価することができる。
(注) 「取得価額」とは、当該財産の取得に要した金額並びに改良費及び設備費の額の合計額をいい、家屋等については、当該合計金額から、評価基本通達130((償却費の額等の計算))の定めによって計算した当該取得の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額をいう。
そこで、評価基本通達130((償却費の額等の計算))の定めは以下:
(償却費の額の計算)
130 前項のただし書の償却費の額を計算する場合における耐用年数等については、次に掲げるところによる。(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)
(1) 耐用年数
耐用年数は、耐用年数省令に規定する耐用年数による。
(2) 償却方法
償却方法は、定率法による。
上の通達は平成元年のもので、おそらく当時は、税務上は、建物も定率法が認められていたと推定する(以下の議論に関係ないので、検証しない)。しかし現在の令和4年度の減価償却制度上は、建物は(旧じゃない)定額法の一択のみ。
他方で、「相続税の節税対策で、限りなくペーパーカンパニーである不動産管理会社を設立し、①管理方式、②転貸方式、③不動産(特に建物)保有方式、のうち、①②から③へ移動するため、個人から法人へ建物を売却(譲渡)する際の売却金額」は、実務上、売却時点までの減価償却後の簿価そのもので、実務上OKとされている。
特に、当該物件はこの通達の13年度の、平成13年に取得しているので、従来、旧定額法で償却してきている。そして、準確定申告の 所得税青色申告決算書(不動産所得)の3ページ目の 〇減価償却費の計算 の表の右端の ヌ 未償却残高(期末残高) が仮に認められるとしたら、上の「建物の取引価額」はダイレクトにこの金額で済む。
以上のように所説が交錯するが、整理すると以下が論点となる:
- 思考停止で「通達は絶対」として上の 定率法 がマストなのか?(そのまき直し計算をする?)
- それとも定額法を読み直すのか?読み直す場合、
- 現在の定額法での巻きなおし計算をするのか?
- 準確定申告の中の、〇減価償却費の計算 の期末座高をそのまま無修正で利用して可なのか?
結論
・準確定申告の中の、〇減価償却費の計算 の期末座高をそのまま無修正で利用して可、
と判断する。
理由
以下の通り:
1.私見
まず、償却計算を適用する以上、しょせん仮定計算であることに鑑みれば、合理的な方法によっていれば許容されるハズと考える。
その合理性の一丁目一番地は、定率法 か 定額法 の選択であろう。そして、平成元年時点で想定されていなかった建物の減価償却方法が定額法に一本化された事実は無視できないと考える。
次に、どの定額法を適用するかであるが、比較でいうならば、直近の定額法を適用(=つまり、まき直し計算)をした方が経済的実態を観念するならばベターかもしれないが、再言であるが、仮定計算でしかないので、課税上の弊害がない事例であれば、従来、所得税等申告で是認されている方法(=この事例の場合、旧定額法)による償却計算でも是認されると考える。
2.(貸家でない)居住用の建物のケースの、書籍の解説
「税理士のための相続税Q&A 贈与税の特例」(飯塚美幸、中央経済社)の、Q25 住宅ローン返済中の居住用財産の贈与」に以下の実務上の扱いが示されているが、その中の「② 家屋等」で計算の具体的な内容が明示されている(★単純な金額例は次のページに示されている)
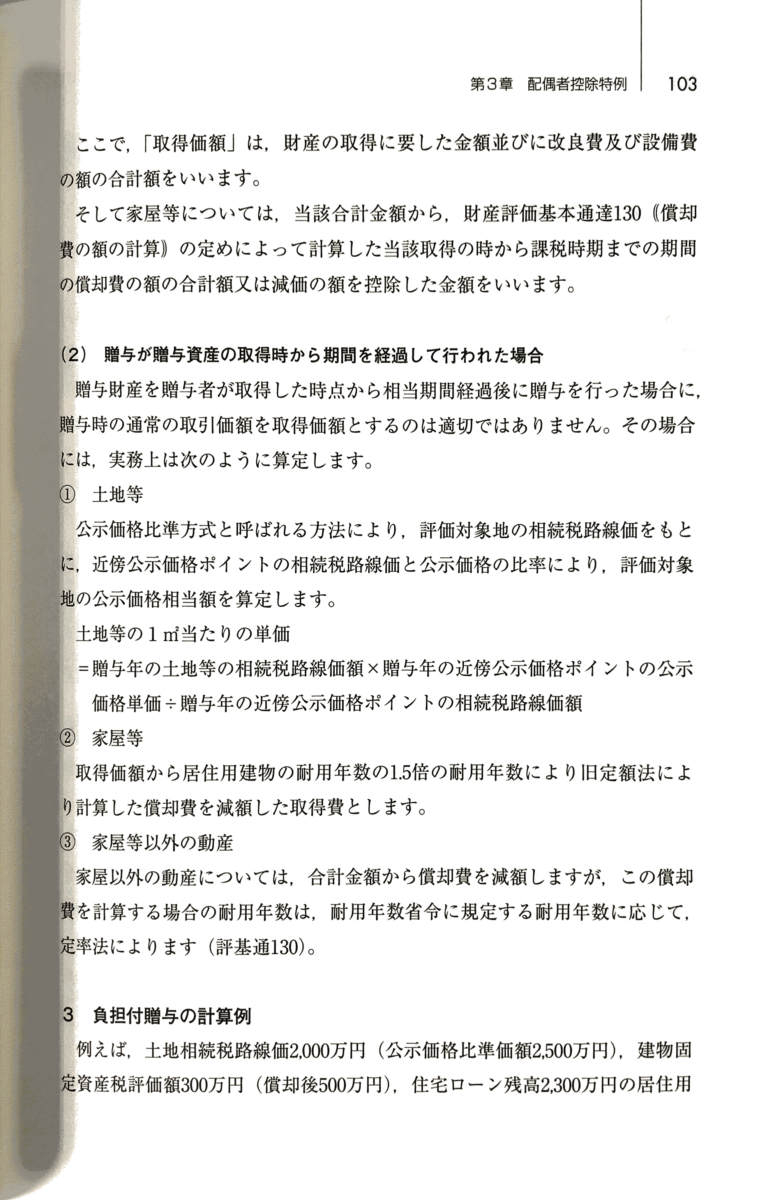
この「② 家屋等」の内容は、私見では以下をベースにしていると推定する:
国税庁hp 「No.3261 建物の取得費の計算」の方を適用する
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
(以下、一部抜粋)
減価償却費相当額は、その建物が事業に使われていた場合とそれ以外の場合では異なっており、それぞれ次に掲げる額となります。
事業に使われていた場合
建物を取得してから売るまでの毎年の減価償却費の合計額になります。
(注1)仮に毎年の減価償却費の額を必要経費としていない部分があったとしても、毎年の減価償却費の合計額とすることに変わりはありません。
(注2)「国外中古建物の不動産所得の損益通算等の特例」の適用を受けた国外中古建物を売った場合には、この建物の毎年の減価償却費の合計額からこの特例により生じなかったものとみなされた損失に相当する部分の金額の合計額を控除した金額となります。
事業に使われていなかった場合
建物の耐用年数の1.5倍の年数(1年未満の端数は切り捨てます。)に対応する旧定額法の償却率で求めた1年当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて計算します。
具体的には、次の算式により計算します。
建物の取得価額×0.9×償却率(※1)× 経過年数(※2)= 減価償却費相当額(※3)
※1 非業務用建物の償却率
(注1)「金属造①」・・・軽量鉄骨造のうち骨格材の肉厚が3ミリメートル以下の建物
(注2)「金属造②」・・・軽量鉄骨造のうち骨格材の肉厚が3ミリメートル超4ミリメートル以下の建物
※2 経過年数の6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます。
※3 建物の取得価額の95パーセントを限度とします。
3.類推適用の妥当性の確認(私見)
実はこの方法で算出された時価は定額法ベースなので、実は定率法ベースよりも時価が高くなってしまう。。。。(この点、相続人には申し訳ない)。だから、税理士的には、むしろ安心な方法。。。
以上の安心を前提に以下、気楽的に検討するに、以上の書籍の解説は、再言であるが「居住用=事業に使われていなかった場合」であるが、これを、今回の事例の「貸家」は立派な不動産事業に該当するため、上の「貸家」に応用するには、上の「事業に使われていた場合」をそのまま適用して問題ないと考える。
つまり、従来の減価償却計算でよく、具体的には、準確定申告の所得税確定申告書の〇減価償却費の計算、の期末残高でOKと考える。
補足
ググっても、書籍を調べても、上の書籍のみ。
■


