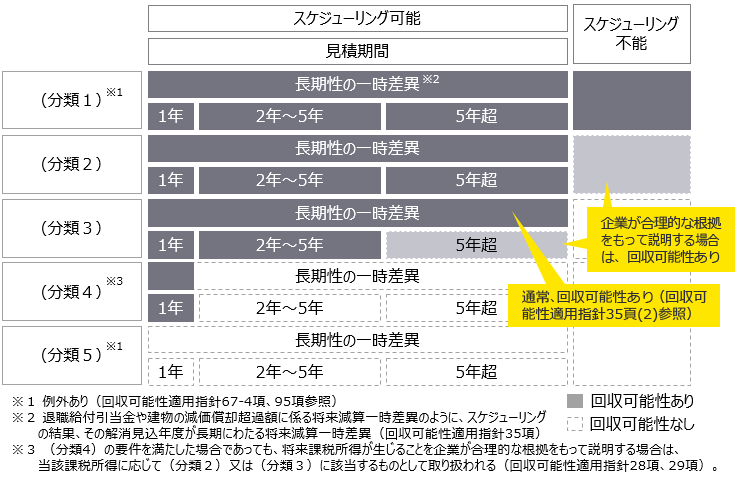E社様用)会社分類1の条件をみたす会社での繰延税金資産の計算上、スケジューリング不能な一時差異もカウントしないといけないの?
問題の所在
以下の事例:
・上場会社
・税効果会計上、いわゆる会社分類1の要件を満たしているので、自身、会社分類1と認識している。
・当社の将来減算(加算)一時差異も、ご多分に漏れず、当然、翌期に解消、長期に解消、スケジューリング不能、の3ケースに大別してスケジューリングされている。
・うち、スケジューリング不能の分は以下のもので、繰延税金資産(負債)には不計上で、評価性引当額に計上している。
役員退職慰労引当金(創業者の会長分)
役員退職慰労引当金(改定分)
投資有価証券評価損
ゴルフ会員権評価損
除去債務
↓
上の点に関し、一般に会社分類1の会社では、全額、繰延税金資産(負債)を認識する/評価性引当額は認識しない、と語られている。
例えば、以下の書籍の文中にある図示も同様である。
結論
上の会社がスケジューリング不能な一時差異と整理し繰延税金資産を不計上な部分は、会社分類1の企業の場合には、繰延税金資産を計上しなければならないと判断する。
★後述の、平成30年の改正前の適用指針の記載ぶりからは、スケジューリング不能な部分も、会社分類1の場合には繰延税金資産に計上することになっていた。平成30年の改正でも、それは不変であると判断した。
理由
・まず、適用指針の内容としては、平成 30 年改正適用指針において、(分類 1)に該当する企業において、将来の状況により税務上の損金に算入されない項目に係る一時差異について、例外的に回収可能性がないと判断する場合があることを明らかにするため、繰延税金資産の全額を回収可能性があるものとする取扱いに、「原則として、」との文言が追加された。
・その上で、上のスケジューリング不能な分、将来必ず損金算入されるため、繰延税金資産を計上する必要がある。
役員退職慰労引当金(創業者の会長分)→ 逝去したときに支払い、損金になる。
役員退職慰労引当金(改定分)→ 不祥事等で受取辞退でもない限りまず満額支給でしょうし、その時に損金になる。
投資有価証券評価損 ★当社の存続中には絶対に売却しない、という方針はない。売却時に損金になる。
ゴルフ会員権評価損 ★当社の存続中は絶対に売却しない、という方針はない。売却時に損金になる。
資産除去債務(負債) ★以下の記事の通り、スケジューリング可能な分と整理されるので、将来の退去時の支出時に損金になる。
(以下、一部抜粋)
- 35. 退職給付引当金や建物の減価償却超過額に係る将来減算一時差異のように、スケジューリングの結果、その解消見込年度が長期にわたる将来減算一時差異は、企業が継続する限り、長期にわたるが将来解消され、将来の税金負担額を軽減する効果を有する。これらの将来減算一時差異に関しては、第15項から第32項に従って判断した分類に応じて、次のように取り扱う。
- (1) (分類1)及び(分類2)に該当する企業(第28項に従って(分類2)に該当するものとして取り扱われる企業を含む。)においては、当該将来減算一時差異に係る繰延税金資産は回収可能性があると判断できるものとする。
(中略)
・結論を先に示すと、資産除去債務について各分類における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いを示すと<表1>であり、第35項と比較すると、分類1及び分類4は一緒、分類2では理屈が異なるが結論は同じであり、分類3ではスケジューリングが可能な分のみが回収可能であるため結論も異なる。
======================
↓
「原則として、」とあるので、計上しない例外部分があることは承知するが、それは、(分類 1)に該当する企業において、将来の状況により税務上の損金に算入されない項目に係る一時差異 に限定される。
★後述するが、検討の結果、上で会社のスケジューリング不能としたものは将来、必ず損金に算入されるので、「会社分類1の会社でスケジューリング不能分を繰延税金資産を計上しないのはマチガイ」となる。
↓
以下の、企業会計基準適用指針第 26 号 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(平成 27 年 12 月 28 日、最終改正平成 30 年 2 月16 日、企業会計基準委員会)
https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/zeikouka20221028_16.pdf
で、該当する箇所は以下の通り ★なおこの直前の改正版から変わっている点(=改正点)を赤着色した)
((分類 1)に該当する企業の取扱い)
17. 次の要件をいずれも満たす企業は、(分類 1)に該当する。
(1) 過去(3 年)及び当期のすべての事業年度において、期末における将来減算一時
差異を十分に上回る課税所得が生じている。
(2) 当期末において、近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれない。
18. (分類 1)に該当する企業においては、原則として、繰延税金資産の全額について回
収可能性があるものとする。
((分類 1)に該当する企業の取扱い)
66. 本適用指針では、(分類 1)に係る分類の要件について、「期末における将来減算一時
差異を十分に上回る課税所得を毎期(当期及びおおむね過去 3 年以上)計上している
会社等で、その経営環境に著しい変化がない場合」とする監査委員会報告第 66 号の定
めの内容を踏襲している(第 17 項参照)。なお、(分類 1)に係る分類の要件として示
している「当期末において、近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれない。」(第
17 項(2)参照)とは、監査委員会報告第 66 号における「その経営環境に著しい変化が
ない」を踏襲したものである。当該要件は、通常、近い将来に課税所得を獲得する収
益力を大きく変化させるような経営環境の変化が見込まれない場合、将来においても
一定水準の課税所得が生じると予測できる状況にあることを意図している。
67. (分類 1)に該当する企業においては、「通常、当該会社が、将来においても一定水
準の課税所得を発生させることが可能であると予測できる。したがって、そのような
会社については、一般的に、繰延税金資産の全額について、その回収可能性があると
判断できる。なお、この場合には、前述 4.のスケジューリングが不能な将来減算一時
差異についても、将来スケジューリングが可能となった時点で課税所得が発生する蓋
然性が高いため、当該将来減算一時差異に係る繰延税金資産については回収可能性が
あると判断できるものとする。」とする監査委員会報告第 66 号の定めの内容も踏襲し
ている(第 18 項参照)。
67-2. 税効果適用指針を審議する過程で、完全支配関係(法人税法第 2 条 12 の 7 の 6 号)
にある国内の子会社株式の評価損のように、当該子会社株式を売却したときには税務
上の損金に算入されるが、当該子会社を清算したときには税務上の損金に算入されな
いこととされているものについて、当該子会社株式を将来売却するか、当該子会社を清
算するか等が判明していない場合に、一時差異(将来減算一時差異)として取り扱うか
否かが明確ではないとの意見が聞かれた(税効果適用指針第 80 項)。
67-3. これについては、当該子会社株式を将来売却するか、当該子会社を清算するか等が
判明していない場合であっても、個別貸借対照表に計上されている資産の額と課税所
得計算上の資産の額との差額は、当該差額が解消する時にその期の課税所得を減額す
る効果を有する可能性があることから、本適用指針第 3 項(3)に定める一時差異が解消
する時にその期の課税所得を減額する効果を持つものに含め、一時差異(将来減算一時
差異)に該当するものと整理することとした(税効果適用指針第 81 項)。
67-4. これに関連し、例えば、完全支配関係にある国内の子会社株式の評価損について、
企業が当該子会社を清算するまで当該子会社株式を保有し続ける方針がある場合等、
将来において税務上の損金に算入される可能性が低い場合に当該子会社株式の評価損
に係る繰延税金資産の回収可能性はないと判断することが適切であると考えられる。
したがって、平成 30 年改正適用指針においては、(分類 1)に該当する企業において、
将来の状況により税務上の損金に算入されない項目に係る一時差異について、例外的
に回収可能性がないと判断する場合があることを明らかにするため、繰延税金資産の
全額を回収可能性があるものとする取扱いに、「原則として、」との文言を追加した(第
18 項参照)。
67-5. また、第 67-2 項から第 67-4 項に関連し、平成 30 年改正適用指針の公開草案に寄せ
られたコメントの中には、税効果適用指針において子会社株式等に係る将来加算一時
差異に関する取扱いを見直しているため、(分類 1)に該当する企業において繰延税金
資産の回収可能性はないと判断される例外的な取扱いとして、前項における完全支配
関係にある国内の子会社株式の評価損に係る将来減算一時差異だけではなく、子会社
株式等の評価損に係る将来減算一時差異も対象としてはどうかという意見があった。
この点、将来減算一時差異に係る繰延税金資産の回収可能性については、第 63 項の
とおり、本適用指針では、監査委員会報告第 66 号における企業の分類に応じた取扱い
の枠組みを基本的に踏襲しており、平成 27 年適用指針では、(分類 1)に該当する企業
において、スケジューリング不能な将来減算一時差異に係る繰延税金資産を含め、「繰
延税金資産の全額について回収可能性があるものとする。」としていた。
スケジューリング不能な将来減算一時差異に該当する子会社株式等に係る将来減算
一時差異は、将来の状況により税務上の損金に算入されない項目に係る一時差異の取
扱い(第 67-4 項参照)と異なり、将来のいずれかの時点で損金に算入されるものであ
る。
(分類 1)に該当する企業において、当該将来減算一時差異に係る繰延税金資産ま
で回収可能性がないものとして取り扱うことは、スケジューリング不能な一時差異(第
3 項(5)参照)に係る繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いを見直すことにつなが
り、平成 27 年適用指針において監査委員会報告第 66 号における企業の分類に応じた
枠組みを基本的に踏襲している趣旨と整合しないと考えられる。
したがって、(分類 1)
に該当する企業における子会社株式等の評価損に係る繰延税金資産の回収可能性に関
する取扱いについては変更しないこととした。
==========
補足
なお以下のEY新日本の記事は、ベースは改正前であるが、上の改正点が加筆されている!さすが (^o^)
★なお以下の引用中の※1の中で、95項を引用しているのは、会社分類5についてであり、ここではスルーでOK:
税効果会計(平成27年度更新) 第4回:繰延税金資産の回収可能性
税効果会計(平成27年度更新) 第4回:繰延税金資産の回収可能性 | EY Japan
(以下、一部抜粋)
(1) (分類1)に該当する企業の取扱い
過去(3年)及び当期の全ての事業年度において、期末における将来減算一時差異を十分に上回る課税所得が生じており、かつ、当期末において、近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれない企業(以下、「(分類1)に該当する企業」)は、通常、将来においても一定水準の課税所得が生じると予測できるため、原則として※1、繰延税金資産の全額について回収可能性があるものとされます(回収可能性適用指針17項、18項)。
(引用者中略)
3. 企業の分類ごとの繰延税金資産の計上可能範囲のイメージ
企業の分類ごとの計上可能な繰延税金資産の範囲のイメージは下図の通りです。
<図表>